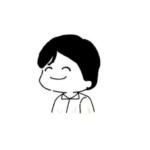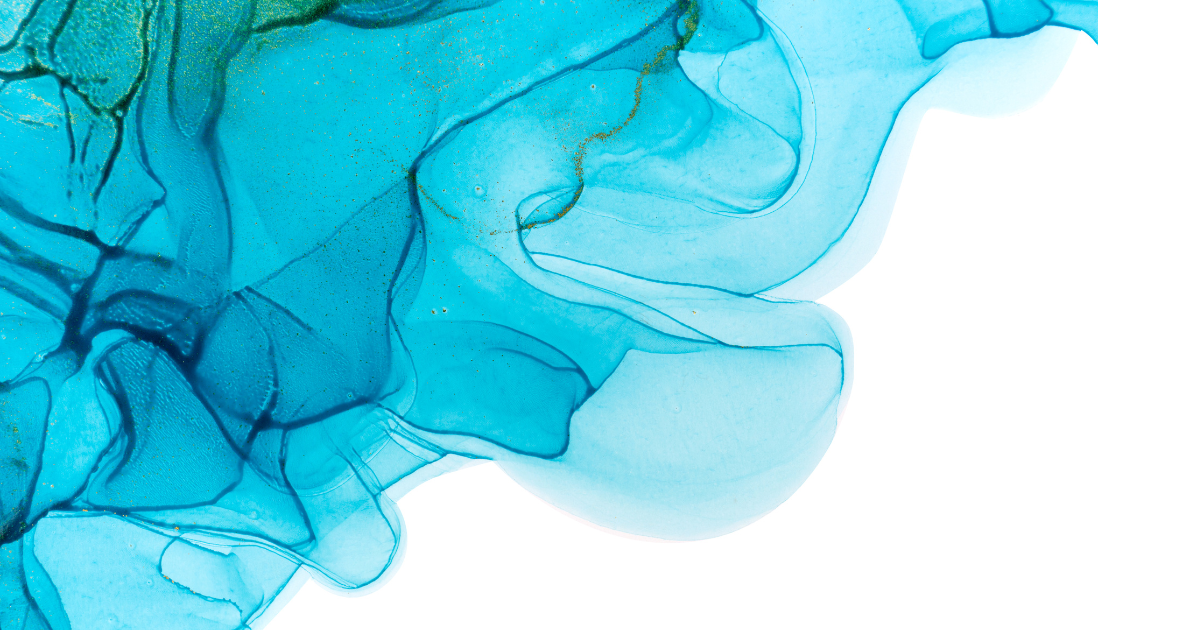なぜ本を読むのが苦手だった私が、読書好きになったのか。
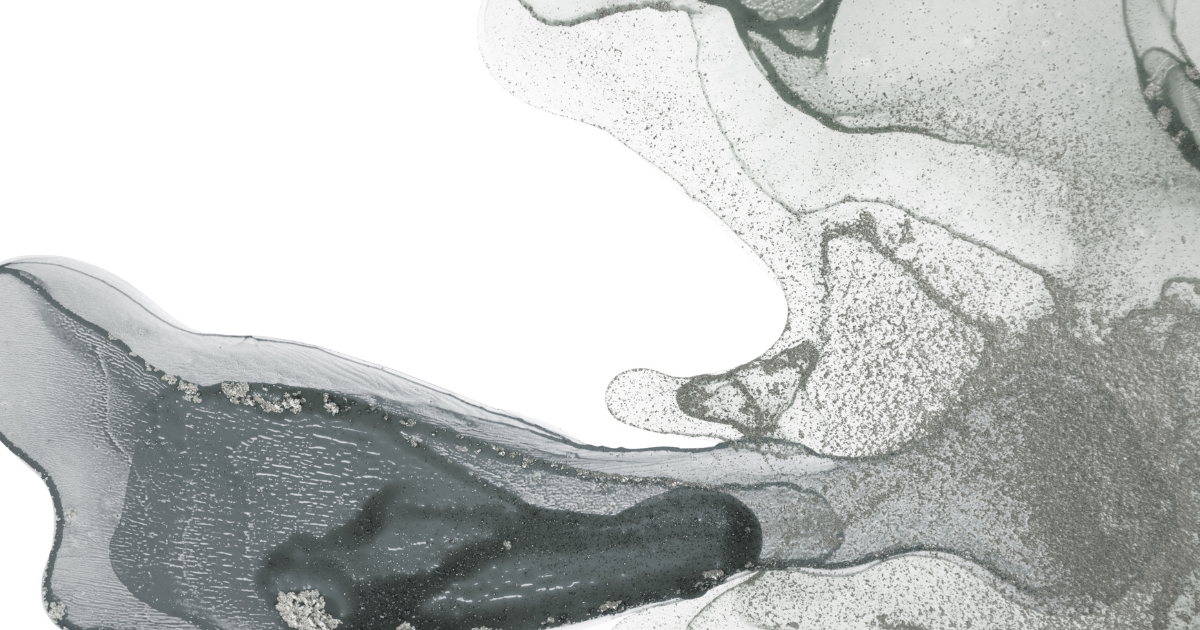
今までの自分では想像もできなかった、“読書好き”の自分
私はこの数か月で、信じられないぐらいの読書好きとなった。
私にしてみればとてもじゃないが、自分がこんなに本を読むようになるとは思わなかった。
本とは無縁の人生
今までの私の人生は、「本」とは無縁の人生であった。
幼少期、私は「テレビ」で育ったのである。
私はただひたすらに、アンパンマンを見ていた記憶がある。
ほんとうに、ただひたすらに….。
ただ、これ以上私が幼少期、何をしていたのか、
アンパンマンの他に何を見ていたのか。などはほとんど覚えていない。
いずれどこかでお話するかもしれないが、私は中学校3年生より前の記憶を、
ほぼ抹消した過去があるからである。
それはさておき、私は本当に、今までずっと本とは無縁の生活であった。
しかし思い返せば、私はあることをきっかけに、“文章”には触れるようになっていったことを回顧する。
高校での、“文章”に触れる機会
私の高校生活はを振り返ると、今思えば、
「現代文」という教科を相当に深く勉強していたことに気づかされる。
高等学校における「現代文」の授業の特徴は、
1つの評論・小説に対して、“極めて長い時間をかけて”読解していくという特徴がある。
そして私は、定期テストで高い点を取りたかったから、
必然的に「現代文」のテストで点を取るためには、先述に則って、
1つの評論・小説に対して極めて“深く”読み込んだのである。
今思えば、この経験は後の私にとって、とても重要な能力を養うきっかけとなったと思っている。
“文章読解力”の重要性
私はプロフィールや他の記事でも、
「自分は国語と社会の先生を目指す」と豪語している。
私の1番好きな科目は、圧倒的に「社会」である。
「社会」ほど、面白い教科はないと、今でも思っている。
しかし私は、特に高校3年生から今までで考えを巡らせていくにあたって、
「国語」、特に“文章読解力”の重要性を強く意識するようになった。
これは断定したいと思う。
人間にとって1番重要な能力は、“文章読解力”である。
今現在(2024/9/8)時点では、私はそう思っている。
今私が、ここ数か月で急激に読書が好きになったのも、
私が今こうやって記事を書けているのも、
すべて、高校で培った「国語力」特に“文章読解力”のおかげであることは間違いがない。
そして私は、どの場面でも、何をするにしても、
「人間の根幹には“文章読解力”が必然である」、と私は思っている。
私の昔の友人に、数学が得意だと言っていた友人がいた。
しかしその友人は、ある一定のラインで高止まりしていた。
その友人は、本当に国語が苦手だったのである。
だから、数学の「文章問題」というのがなかなか解けなかったのだ。
そもそも本当に数学が苦手の私には、全くわからないのだけれど、
彼が最後まで数学で山を越えられなかったのは、
「文章問題」といった、応用問題が解けなかったから。
そしてそれは、彼にはその文章を理解・把握する力がなかったから。
なのだと、私はとても偉そうな口ぶりだが、回顧する。
「本」を読み始めるきっかけ ~随筆~
私は2024年6月、大病を患った。
そしてその時、私は「本」に手を出し始めたのである。
その時私が読み始めた本は、今でもそれをたくさん読むのだが、
いわゆる「自己啓発本」であった。
私はその時、はっきり言って「人生」というものに絶望していた。
だから私は、“生きる力”か何か?
いや違う、その時はもう暇つぶし感覚で「本」という選択肢しかなかったのかもしれない。
そして読むのなら、“人生に関する本”や、“生き方に関する本”を読もう、と思ったのだと思う。
そのスタンスは今も変わらない。私は今でも、主に“生き方に関する本”を主に読んでいる。
「自己啓発本」であったり、あとは「エッセイ」である。
私は本当に「エッセイ」、すなわち“随筆”が大好きである。
だから私も、このブログの大本は「随筆」となっている。(今のところは。)
随筆とは、“鏡”である。
私が随筆を好むのは、随筆には、
「その人の生き方が映し出されている、“鏡”である」と思うからである。
随筆とは、“鏡”なのである。
私が随筆をこのブログに書く時もそうであるし、
日課である「日記」を書く時もそうであるが、
これらを書く時は必ず、“自己の内面を見つめる”という作業を伴う。
そしてその内面が、文字となって文章に映し出されていくのである。
「文章に映し出されていく」というのは、言葉遣いは間違っているかもしれないが、
“表現”としてはとても適切であろうと思う。
その自己の内面が映し出された文章たちは、その人の“人生”を映している。
随筆は、「自分を見つめるもの。」
随筆には、読み手・書き手それぞれに、「自分を見つめる」という過程があると思う。
読み手は、その随筆から、その人の“人生観”を知り、自己と比較していく過程で自分を見つめる。
書き手は、自らの過去や想いを、“書く”と言う行為でもって自分を見つめる。
どちらも、自らの心の内面に光をあて、「自己を見つめる機会」を我々に与えてくれるのである。
随筆は、“人生観の比較”である。~「自己啓発本」と「随筆」~
「自己啓発本」も、ほぼ同じ作用があるといえる。
しかし随筆には固有の特徴として、“人生観の比較”という特徴があると私は感じている。
「自己啓発本」は、「こうするといいよ。」というような、
なにか、「教え諭すようなもの」というのを感じる。
私は「自己啓発本」をけなしているわけではない。
しかし、「自己啓発本」と「随筆」には、ちょっとした性質の違いを感じる。
「随筆」、すなわち「エッセイ」を読んでいると、
その筆者の世界に入り、その中で自らの思考との比較をおこなう。
それは、私にとってはとてもクセになる行為だ。
だから私は、随筆が好きだ。
私の今後
おそらく私は、今後も随筆、すなわち“エッセイ”を好んで読み、
また、このブログを使って自らも書いていくであろう。
もちろん、随筆だけ読むのではなくて、自己啓発本なども含めて、いろんな本をよむだろう。
しかし改めてになるが、自分がこのように、
一括りにすると「本」というのを好んでいくようになったのは、
絶対的に高校生時代に培った、“文章読解力”のおかげに他ならない。
いずれまた別の記事で、文章読解力については話そうと思う。
しかし若干この記事にも記したが、
“文章読解力”の鍵は、「どれだけ深く読んだ経験があるか。」
という点に依拠するであろう。
まぁ、その点はまたいずれ。
これからもきっと、私は自分の読書ワークを続けていくであろう。[2024/9/8]