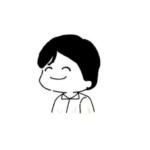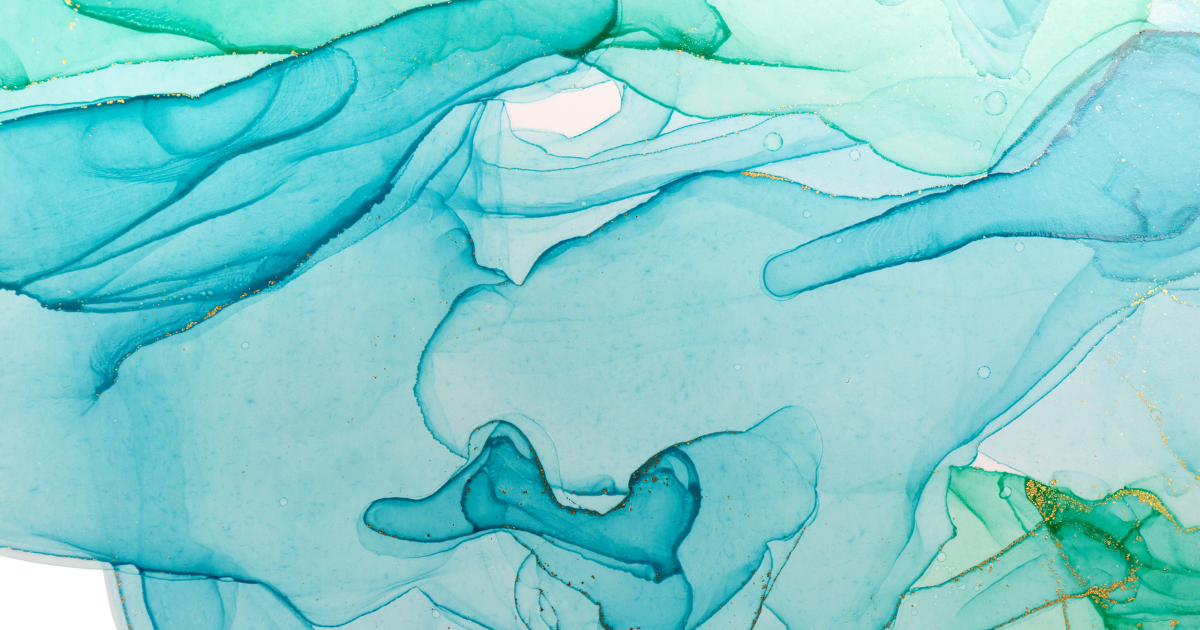「同情」と「共感」の違い

駅の道中にて、ある本と出合う。
私は2024年8月下旬、とある駅にて、
乗り換えの電車を待っていた時に寄った書店で、とある本を手に取った。
齋藤孝氏著『ニーチェ 自分を愛するための言葉』という本である。
私はその時、次の電車が迫っていたため、ほぼ即断即決で購入した。
しかしこの本は私にとって、大きく考えさせられるものを与えてくれた著書であった。
『ニーチェ 自分を愛するための言葉』について
当著書は、明治大学の齋藤孝先生が、思想家「ニーチェ」の言葉を紹介しながら、
ニーチェの思想を基に“生き方”を考えさせてくれる著書である。
この本の論旨を1言で表現するならば、「自分を愛する。」である。
私はこの本から、生きるうえでの“勇気”と言うか、“活力”をいただいた。
それは、そもそものニーチェの思想・1つ1つの言葉が我々に与える自己肯定感と、
それを解説し、論じる齋藤先生の紡ぐ言葉とが、折り重なって生まれたものであると感じる。
事実私も先述の通り、当著書からは「自分を愛する。」ということの大切さを教わった。
素晴らしい名著であり、私は当著書を皆さんに推薦したい。
たった4ページだけ感じた“違和感”
同情と思い上がり
私は当著書を絶賛するが、たった4ページ、たった1つの小段だけ、
ざっとこの本を読んでいくにあたって、“どうしてもぬぐい切れない違和感”を感じたのである。
それが、当著書P85~P88の、「同情と思い上がり」という小段である。
この4ページについて、簡単に概説させてもらうと、
安易な「同情」は“軽視”になり得、「同情」によってお互いを低めあってしまう。
そして齋藤氏は最後に、
『同情によってお互いを低め合う、そんな関係は「真の友情」ではない」』と論を結んでいる。
私は全体を通してこの4ページだけが、どうしても“違和感”がぬぐえないのだ。
なにが引っかかっているのかというと、
「では、“共感”って何???」となったのである。
「共感」とは?
齋藤氏のこの4ページを拝読して
私は徐々に論理的整合性に疑問を持ち始めたのである。
このニーチェの思想を基にした齋藤氏のこの4ページをそのまま受け取った時、
「我々はどのように“共感”をすればよいのか。」と。
さらに言えば、「同情と共感って、何が違うのだろう。」と。
そう、思考を巡らせるようになった。
ニーチェ及び、それを基にこれを記した齋藤氏のおっしゃることはごもっともなのである。
安易な「同情」は“軽視”になり得る。適当に同情する言葉を投げかければ、
それによってお互いを低め合っていってしまう、確かにそれは事実だ。
だがしかし、それでは“共感”というこの2文字は、どう説明すればよいのだろうか。
“共感”の重要性
私は、“共感”というのは、人間にとってとても重要なものであると捉えている。
人は時に、どうしても耐えられないような苦しみに打ちひしがれ、
例えば「うつ病」や「適応障害」、そして最悪の場合「自死」を選択する場合もある。
私たちがそのような苦しみを感じている方々に対して必要なものこそが、
「寄り添う」という行為の中に内包された、“共感”である。
もっとも大切なこと、「寄り添う」
「寄り添う」、ある人が苦しみを感じている時、
我々がしなければならないことであり、その人が最も欲していることである。
私は断言する。本当に人が苦しい時、人間は人に頼る力すら、なくなる。
そしてその時必要なのは、周りの人たちがそれに気づき、「寄り添う」ことである。
それが残念ながら不可能であったり、発見が遅く、重症化してしまうこともある。
事実この記事を書いている私がそうだから。
だからこそ上記のことは、はっきりと断言することができ、
確固たる自信をもって世の中に伝えられるだけの自信がある。
その「寄り添う」ということの過程において、
私は“共感”を、とても重要なこととして位置付けていた。
それが、齋藤氏の著書の4ページによって揺さぶられたのである。
しかし私は、1つの結論というか、自分の中での心の決着をつけた。
“共感”は必要なもの、“同情”は必要のないもの
上記が、私の結論である。これについて詳説する。
人が本当に苦しくて、助けが必要であるとき、
我々は“共感”を含めた「寄り添う」というサポートは、絶対にしなければならない。
「“共感”は必要なもの」なのである。
その上で私は「共感」とは、
「その人の心の中に入っていき、その人の立場にたって全面的にサポートすること。」
であるという風に考えた。「ケアすること」とも言えるかもしれない。
一方「同情」は、齋藤氏がおっしゃったように、
“安易な”同情は軽視になり得、場合によってはお互いを低め合ってしまうものである、というのは、
全くその通りであると感じたことは、先述の通りであるが、
本当に苦しい思いをしている人には、その時には、絶対に言ってはいけない内容であると結論付けた。
齋藤氏の論から則れば、「“同情”は必要のないもの」と言える。
私は1つの言葉から、「共感」と「同情」の違いを自分なりに表してみたいと思う。
「うんうん、そうだよね。」から見る、“同情”と“共感”の違い
「うんうん、そうだよね。」
これは、「同情」・「共感」の双方で使われるであろう典型的な言葉なのではないだろうか。
“共感”における、「うんうん、そうだよね。」
本当に苦しい思いをしていて、辛い状況下に置かれている人たちに、
この言葉を投げかけると、彼らはこのように感じるであろう。
「自分の気持ちなんてわからないくせに。」
これは実体験に基づくものである。私もいろんな方から、その言葉をいただいた。
本当に人が苦しい時、どんな言葉をかけたとしても、なかなか響かないものである。
これは、他のうつ病体験者からの話をきいても、このように思う方が多い。
しかしだけれども、その苦しんでいる当人は、その声掛けを必要としているのである。
これがとても大切なポイントである。
「自分の気持ちなんてわからないくせに…」と思ってしまうが、
無意識的に、半ば本能として当人は“助けを求めている”のである。
私たちはその「心からのヘルプ」を見逃してはいけない。
私たちは先述したように、その人の心の中に入っていき、
その人の立場にたって全面的なサポートをしなければならないのである。
“同情”における、「うんうん、そうだよね。」
私は思索しながら、「共感」と「同情」という2つの言葉の表現の違いを、
その時々の状況を勘案して使い分けることが大切なのではないか、と感じた。
「同情」という言葉が使われる状況は、お互いが精神的に安定している状況下で、
「うんうん、そうだよね。」といった言葉により、
その言われた側はその言葉に甘えてしまい、「自らの成長曲線にストップをかけること。」が、
「同情」という言葉が使われるに値する状況なのではないだろうか。
ここにおいて必要なのは、ただ「同情」するだけでなく、
齋藤氏の著書でも直接的な表現はなかったが、おそらく齋藤氏が伝えたいことなのであろう、
「お互いに高め合うこと。」なのだろうという風に感じる。
すなわちただ「同情」の言葉を投げかけるだけでなく、“お互いに高め合っていくことができるような、”
「プラスの声掛け」というのが必要である。ということなのではないだろうか。
先程「“同情”は必要のないもの」と記したと思う。
ただ、“同情”が絶対悪なのではなく、「“同情”だけではダメだ。」ということなのではないだろうか。
おわりに ~私がこれを書こうを思った理由~
今まで、“同情”と“共感”について、私の思索を言葉に綴ってきた。
本当に辛く、苦しく、限界なところにいる人に対して、
私たちは絶対に「寄り添う」と言うことをしなければならない。
その「寄り添う」の一環の中に、“共感”がある。
“同情”は、ただ同情の言葉を投げかけるだけではなく、
「プラスの声掛け」を付け加えて、お互いを高め合えるものにしなければならない。
これが、「同情」と「共感」の違いではないだろうか。
正直自分でもまだ整理がついてない面があり、とても稚拙であるという風に感じている。
しかし私がどうしても、齋藤氏のこの4ページに違和感を覚え、
このように思索にふけるにいたり、このように記すに至ったにおいては、
やはり世の中にたくさんいる、苦しんでいる人たちの存在があったからだと思う。
私も、私以上に苦しい思いをなさっているかたのことを勘案したとしても、
1人の、辛い体験をし、病魔に襲われ、非常に苦しんだ人間としての、
心からの、「訴えなければならぬ。」という、重要なメッセージなのだったのかな。と、
想いながら私は今このように筆をとり感じている。[2024/9/10]